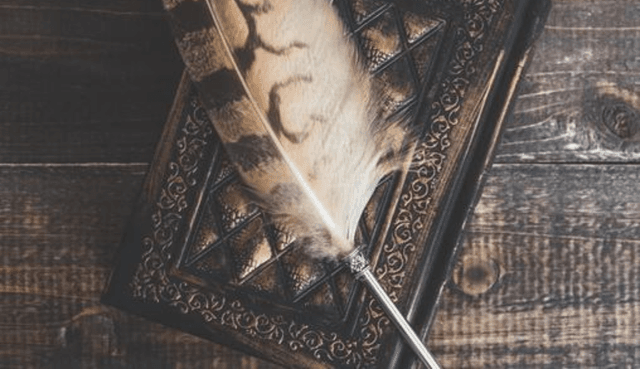ケース面接とは?対策方法や例題を戦略コンサル内定者が一から徹底解説
更新日:
目次
「ケース面接」とは何か
ケース面接とは
ケース面接とは、「ある家電量販店の売上を向上させるには?」「地球温暖化を抑制するには?」というような、面接官に与えられたお題(ビジネス上の課題や社会問題など)に対して、制限時間内で仮説を立て、論理的に回答・ディスカッションをする形式の面接です。
コンサルティングファームなどで出題されることが多いケース面接は、論理的思考力だけでなくコミュニケーション能力、柔軟な思考力、仕事の適性など幅広い要素が測られます。
本記事では、ケース面接について問われる内容から求められる能力、対策の方法まで一から解説していきます。
ケース面接の種類
まずケース面接で実際に問われる内容について解説します。テーマは以下の3つに大別されます。
①経営課題系
②社会問題系
③抽象系
それぞれもう少し具体的に解説していきます。
①経営課題系
一般にケース面接は経営課題系のお題が問われます。具体的に以下のような形式で問われることが多いです。
・フェルミ推定(売上・市場規模などの推定)
・売上向上
・利益向上
例)冷蔵庫の市場規模を推定せよ/家電量販店の売上向上施策を立案せよ/都内のカフェ一店舗の利益向上施策を立案せよ
②社会問題系
社会課題系のお題は頻度は高くありませんが出題されます。ファームが公共系の案件に強みを持っていると出題されやすい傾向があります。
例)日本のCO2排出量を削減する方法を構造的網羅的に述べよ/地方都市の衰退の要因は何か?それを改善する施策を立案せよ
③抽象題系
抽象系のお題を問うファーム、問われる機会はほとんどありません。しかしディスカッション中に文脈に沿って哲学的な問いを投げかけられることはあります。
例)愛とは何か?企業の存在目的は何か?宗教の成立条件は?
戦略コンサル選考等におけるケース面接の目的と位置づけ
ケース面接の出題意図
ケース面接は”正解のない課題”を解く過程を見ることによって、受験者の思考力・コミュニケーション能力・仕事への適性の判断です。
ケース面接は基本的に面接官と1対1で30分間程度行われ、【出題】→【思考時間(2〜5分もしくは無し)】→【ディスカッション】というような流れで進みます。
思考時間が2〜5分程度、場合によっては思考時間が与えられないこともあるので短時間で思考をまとめて分かりやすく伝えることができるかどうか、建設的なディスカッションができるかということを見極めるために出題されます。
より詳細な求められる能力は後述します。
ケース面接を課す企業の例
コンサルティングファーム・投資銀行・総合商社
選考フローにおける位置づけ
出題頻度が一番高いコンサルティングファームにおいては、選考フローがおおよそ以下の通りになっており、ケース面接はジョブ選考やジョブ通過後の選考に用いられます。
ES→webテスト→筆記/録画→ケース面接→ジョブ(インターン)→ケース面接→内定
コンサルティングファームの選考において非常に重視されており、形式に慣れていないと最善のパフォーマンスができないこともあるので、概要を一通り理解してから臨むようにしましょう。
例題
実際に戦略コンサルティングファームで出題されたことのあるケース面接には以下のようなものがあります。
東京のあるカラオケ店の売上を向上せよ
高速道路の渋滞を解消する方法を考えよ
面接におけるケース面接で求められる能力
ケース面接で求められる能力は思考力・コミュニケーション能力・仕事への適性の3つです。
思考力
思考力は論理的思考力・多面的な思考力・構造化力・仮説思考力の3つに分けられます。
論理的思考力
論理的思考とは、物事を体系的に整理し、矛盾や飛躍のない筋道を立てる思考のことです。ロジカルシンキングとも呼ばれます。
この矛盾や飛躍のない、というのは”客観的に見て納得できる”ということです。論理的思考はケース面接に限らず、あらゆるコミュニケーションをとる上で最低限必要な能力です。
多面的な思考力(幅だし)
ケースでは多角的・多面的に事象をとらえることが求められます。
例えば、「A社の利益が低下している原因」を考える際には、まず「売上」と「コスト」のどちらが変化しているのか?という二つの側面を見たうえで、売上に問題がありそうな場合、さらに売上が減少する要因として以下のように様々な面から見ることができます。
「①市場自体が減少しているのか?」「②自社のシェアが減少しているのか?」
「①既存顧客(リピーター)からの売上が減少しているのか?」「②新規獲得からの売上が減少しているのか?」
「①顧客数が減っているのか?」「②1人当たりの利用(購入)回数が減っているのか?」「③1人当たり1回当たりの利用単価が減っているのか?」
このように一つの問題に対しても観点は無数に存在しますが、意味のある観点をどれだけ挙げられるのか?ということはケースにおいて非常に重要になります。
構造化力
構造化とは物事を構成要素ごとに分解し、構成要素間の関係を分かりやすく整理することです。
先に述べた多面的思考をして十分な幅だしを行うと、様々な情報が整理されていない状態でばらばらに存在することになります。その要素を抽象化してまとめたり、分解する切り口をより適切なものにしたりすることによって、分かりやすく整理する必要があります。
構造化の際に重要なのは①MECE(ミーシー)に分解できているか?と①その場に適した構造化になっているか?です。
①MECE(ミーシー)とは”もれなくダブりなく”という意味でMutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの略です。
MECEでない構造をつくって話を進めてしまうと、議論できていない要素(もれ)が生じたり、どちらに分類して考えたらよいか分からない要素(ダブり)が生じたりするため論理的な議論が出来なくなってしまいます。
②ケース面接ではMECEであることを意識するあまり、意味のない切り口で分解した構造を作ってしまうというミスを犯す場合があります。”意味のある切り口”とは分解したセグメントごとに量的・質的な差異が十分にある切り口のことです。
「男女」「年齢」などはMECEに分解し易い要素であるため、よく考えずにこれらで分解する人がよく見受けられます。
例えば、スポーツドリンクの顧客を分解する際に「男女」や「年齢」で分けたときに有効な差異が生まれるでしょうか?どんな切り口で分解すればセグメントごとの差異が生まれるかを考えてみてください。
仮説思考力
仮説思考とは、情報収集や分析を実行する前に仮説(現在得られている情報から導き出される最も妥当な結論)を立て、最終目的や成果物の形を常に意識しながら情報収集や分析を行い、仮説の検証と修正を繰り返して最終的な結論に至るという思考方法です。
具体的な例としてよく取り上げられるのは研究です。研究者は実験をする前に仮説(実験結果はこうなるであろうという予測)を立ててから実験を行い、その仮説が正しいかどうかを検証します。もし仮説通りの結果にならなかった場合でも、そうならなかった要因の仮説を改めて立てた上で実験を繰り返します。
仮説思考は短時間で成果を出すうえで極めて重要な思考方法であり、実験を行う研究だけでなくビジネスの場でも重視されます。特に短期間で高い水準のアウトプットが求められるコンサルタントには必須の思考法であるため、面接でもこのような考え方ができているかどうかが問われます。
ケース面接では限られた時間の中で説得力のある解答をする必要があります。
仮説がない状態で問題を一から網羅的に考えていくと、時間が足りないだけでなく解答の精度も落ちてしまいます。解答中は常に、その問題の着地点(結論)を事前に想像しながら思考を深めるようにしましょう。
コミュニケーション能力
ケース面接では思考力だけでなくコミュニケーション能力も求められています。
一般にこのコミュニケーションは軽視されがちですが、どんなに思考力が優れていようとコミュニケーションが十分に取れないと判断された場合は選考の通過は難しいでしょう。
求められるコミュニケーション能力は人間性、情報伝達能力、傾聴力・理解力の3つに分けられます。
人間性
ケース面接は一般の面接とは違い、人間性を直接問うような質問はありません。しかし、入社する人を選考している以上”一緒に働きたいか?”という感覚は大事にされており最低限の礼儀や気遣いは必要です。
情報伝達力(わかりやすく話すことができるか?)
どんなに優れた思考をできていても、伝わらなければ考えていない人と同じ評価になります。
そこで重要になってくるのが以下の2つです。
①結論ファースト
②構造化して話す
①結論ファーストは話す内容の結論を最初に述べることです。ディスカッションをしているとその場で返答しなければいけない状況になり話が冗長になってしまうことがあります。思考時間が短くても結論を最初に述べ、そのあとにその発言の根拠を述べるようにしましょう。
②先に述べた構造化は、自分の頭を整理するだけでなく、自分の考えを相手に伝える際に非常に有効です。具体的な話を始める前に、「要因は3つあります。1つ目は…」というように枠組みを作って話すことによって、自分と相手の頭の中に描いている構造を一致させることでコミュニケーションがスムーズになります。
傾聴力・理解力(相手の発言を聞き理解することができるか?)
ディスカッションをする上で相手の発言をしっかり聞いて理解することは重要です。
特に以下3つの問いに答えられるように話を聞くようにしましょう。
①何について話しているのか?
②質問はどのような返答を求めているのか?
③その発言の裏にある意図は何か?
仕事への適性
知的好奇心
ケース面接が問われる企業、特にコンサルティングファームでは業務の性質上、新しいことや複雑なことに対しても意欲的に取り組むことが求められます。
ケース面接を解いていて「面白い」「なぜこうなっているのか?」「もっと深く考えたい」などの感覚を抱ける人は知的好奇心の面においてはコンサルティングファームに向いてる可能性が高いです。
成長可能性(コーチャビリティ)
新卒採用は入社後どれだけ成長して活躍するか?ということを考慮して採用活動を行います。
そのためケース面接ではディスカッションの中でどれだけ成長できるか?という観点も見られています。30〜60分という短い時間ですが、指摘された点について自分自身でどれだけ修正できるかということが重視されています。
これは1回の面接の中だけの評価だけでなく、選考フロー全体を通じた成長も評価に入る場合があります。
ケース面接の評価ポイント~勘違いされがちな要素~
ケース面接は様々な本が出回っていたり、個人で対策をする間に本質的なことを見失ってしまうことがあります。
最後に評価のポイントでありながら勘違いされがちな要素について解説します。
①「論破」ではなく「ディスカッション」
ケース面接では自分の仮説を面接官に否定されるとそれに反論をぶつけて論破しようとする人が少なくありません。もちろん自分の仮説をサポートするのに最低限の情報は伝える必要がありますが、自分の仮説に固執するあまり、相手の発言を聞き入れない状態になってしまうことはディスカッションにおいて絶対に避けるべきことです。
面接官によってはディスカッションを誘導してもらえるので、自分の仮説にこだわり過ぎず柔軟な思考で建設的なディスカッションをすることを心がけましょう。
②「良い施策」ではなく「プロセス」
ケース面接は単に「良い施策を思いつけばいい」というものではありません。
実際の業務でもそうですが何かを提案する際は、どのような意図で行い、どのような選択肢の中から、どのような理由で”良い”施策であるのか、を相手に適切に伝えられるかどうかが重要です。
そのため、ケース面接ではこのようなプロセスを十分に踏めるかどうか
極端な例ですがほとんど同じような施策を伝えたとしても、そのプロセスの違いや伝え方の違いで評価が大きく異なることは十分にあり得ます。
③「思考力だけ」ではなく「人間性も」
ケース面接を課す企業は単に”頭のいい学生”を欲しいと思われがちですが、実際は人間性もかなり見られています。「一緒に働きたいかどうか?」という観点は常に重視されているため、コミュニケーションは疎かにしてはいけません。
まとめ
今回は「ケース面接」とは?求められる能力は?というテーマで書かせていただきました。
ケース面接とは何か?選考における位置づけや求められる要素は何か?どのようなポイントに注意すれば良いのか?ということが少しでもご理解いただけていれば幸いです。
長文となりましたが、最後までご高覧頂きありがとうございました。